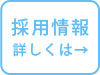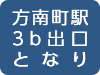福島県生まれ。平成13年4月より東京女子医科大学第一内科(呼吸器科)に勤務する。同院で呼吸器科のほか、消化器内科、循環器内科、神経内科、リウマチ・膠原病内科、内分泌・代謝内科、麻酔科などを回り内科医として一通りの手技やスキルを学ぶ。その後、東京都職員共済組合青山病院、済生会栗橋病院に出向して救急医療から専門にとらわれない内科全般、がん治療や呼吸器・アレルギーの最先端医療まで数々の経験を積み上げる。在宅分野では、平成13年より現在までずっと携わっている。平成20年に在宅支援病院制度を国が制定することを発表すると、全国の病院に先駆けて支援病院を立ち上げるために、日扇会第一病院に籍を移す。その在宅訪問を厚生労働省や各医療機関のモデルケースになるまで成長させた実績をもつ。長年の在宅診療の経験より、内科系に留まらずオールマイティーな診療が可能である。
学会活動・資格
社会的活動
- 東京女子医科大学第一内科非常勤講師
- 杉並区立方南小学校校医
- 杉並区立保育室和泉北園医
- NPO法人日本融合医療研究会理事長
- NPO法人日本メディカルハーブ協会理事
- 一般社団法人日本フィトセラピー協会理事
- NPO法人心とからだの研究会顧問